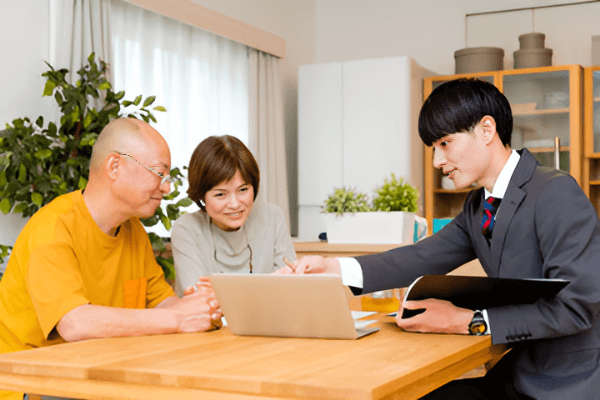建て替えや増改築が認められていない「再建築不可物件」を相続し、どのように対処すべきか分からないという人もいるでしょう。再建築不可物件の相続にはさまざまなリスクが潜んでいるため、なるべく物件を引き継がない方法がベストです。また、相続したあとであれば、手放すことをおすすめします。
本記事では、相続する物件が再建築不可物件だった場合の対処法について、「相続前」と「相続後」の2つのパターンで詳しく解説します。
1.再建築不可物件を相続するリスク

まず、相続する不動産が再建築不可物件だった場合に考えられるリスクを解説しましょう。
①建て替えができない
再建築不可物件は、一度解体してしまうと再建築できません。老朽化や災害などで倒壊してしまった場合は、二度と家を建てられないため、その土地に住めなくなってしまうのです。
②売却しづらい
再建築不可物件は、通常の物件に比べて買い手がつきにくいというデメリットがあります。さらに、物件の性質上、一般的な相場価格よりも安くなりやすいのも特徴です。
もし買い手が見つかったとしても、かなり低い価格での取引となるでしょう。
③税金やメンテナンス費用がかかる
再建築不可物件であったとしても、固定資産税の支払いは必要です。物件のあるエリアによっては、都市計画税も支払わなければなりません。
さらに、建物の老朽化や経年劣化の状態によっては、多額の修繕費用もかかります。
④子孫に悪影響が出る恐れも
再建築不可物件を相続することは、負の遺産を子どもや孫の世代まで引き継ぐことを意味します。
再建築不可物件を何も対策せずに所有し続け、老朽化していると知っていながら適切な修繕を怠って第三者に被害を与えてしまうと、損害賠償請求をされる恐れもあるでしょう。
相続した物件が再建築不可物件かどうかを調べたい人はハウスウェルへ!お問い合わせはこちら
2.相続前にできる対処法
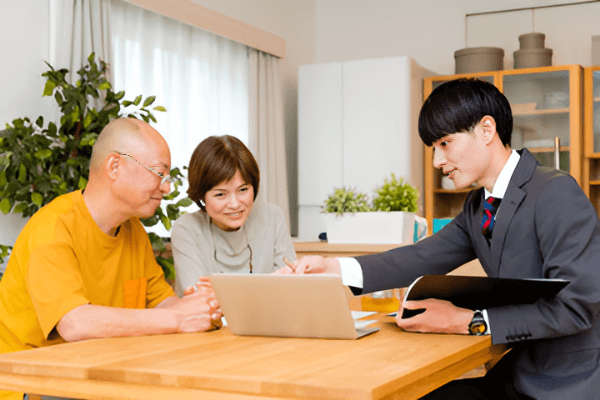
相続前に再建築不可物件だと分かっている場合に、おすすめの対処法をご紹介します。
①相続放棄をする
再建築不可物件を相続すると分かったら、相続が発生したタイミングから「3カ月以内」で「相続登記の名義変更を行っていない」状態であれば、相続放棄ができます。
相続放棄とは、財産や負債の全てを相続しない選択をすることです。
相続放棄をする場合は、次の書類を準備した家庭裁判所に提出します。
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票除表(もしくは戸籍附票)
・申立人の戸籍謄本 |
ただし、相続放棄をする際は、預貯金や株式、宝石などプラスの財産も同時に放棄しなければなりません。「相続放棄をしたものの、実際はプラスの財産の方が多く、損をしてしまった」とならないよう注意しましょう。
②代償分割をする
代償分割とは、1人の相続人が財産を取得して、その相続人が他の相続人に代償金を支払って遺産を分割する方法です。不動産のように現物分割できないケースで活用されています。
例えば、相続人のうち、長女が推定1,500万円の再建築不可物件を相続した場合、他の2人の兄弟に対してそれぞれ500万円を支払って代償分割を行うのです。
ただし、代償分割をする際は、相続人がお金を持っていて代償金を支払えることが前提条件となると理解しておきましょう。
③換価分割をする
換価分割とは、遺産を売却してお金に換え、そのお金を相続人同士で分割する方法です。
一度お金に換えることで、遺産分割がしやすくなります。ただし、再建築不可物件は一般的な物件のようにスムーズに売却できないケースが多く、最悪の場合売却できない恐れもあります。
すぐに現金化できないと、相続人同士でトラブルに発展する場合もあると覚えておきましょう。
再建築不可物件の対処方法は、ハウスウェルにお任せください!お問い合わせはこちら
3.相続後にできる対処法

相続後に再建築不可物件であると判明した場合に、できる対処法をご紹介します。
①リフォームする
再建築不可物件は解体して再建築はできないものの、リフォームはできます。内装や外装を改修したり、設備を最新のものに入れ替えたりして、住みやすい住環境を整えることは可能です。
リフォームの状況によってはそのまま居住することもできますし、売却時に買い手も見つかりやすくなるでしょう。
②隣地の所有者に売却する
隣接する土地の所有者に売却するのも一つの方法です。敷地の拡大や増改築を検討している隣地の所有者がいる場合は、購入を前向きに検討してくれる可能性があります。
ただし、個人間での手続きは非常に複雑なため、売却時に金銭トラブルに発展するケースも少なくありません。契約する際は、不動産会社への仲介を依頼しましょう。
③一定の条件を満たして建て替える
再建築不可物件でも、条件を満たすことができれば建物の再建築が可能です。
再建築を可能にする方法には、次のようなものが挙げられます。
・接道義務をクリアする
・建築基準法第43条ただし書きの許可申請をする |
接道義務をクリアするためには、土地と前面道路の境界線を後退させる「セットバック」や土地の等価交換、さらには隣地の土地を購入したり、借りたりするなどの方法があります。
また、建築基準法第43条のただし書き規定によって、再建築不可物件が一定の条件を満たせば、道路の幅が4メートル未満であっても特例として建て替えできるケースがあります。建築基準法第43条ただし書きの許可申請を希望する場合は、申請の対象となるかを市区町村の窓口に確認・相談しましょう。
④専門の買取業者に依頼する
再建築不可物件は、一般的な不動産業者では対応できないケースが多いため、専門の不動産買取業者に売却する方法がおすすめです。専門業者であれば、リフォームなどの手入れをせずに、そのままの状態でスムーズに売却できます。
業者による買い取りの場合は市場価格よりも安くなる恐れがあるものの、スピーディーに現金化できます。買取実績や相談件数が豊富な不動産業者を探しましょう。
相続した土地の売却や測量問題でお困りの場合は、ぜひハウスウェルにご相談ください。ハウスウェルなら、お客様の不動産の価値を見出して提案や適切なアドバイスをご提供できます。
4.まとめ

再建築不可物件を相続すると、さまざまなリスクが生じます。そのため、できる限りはじめから相続しない、もしくは相続したとしてもなるべく早いタイミングで売却するように検討しましょう。
再建築不可物件の売却を検討している人は、ハウスウェルまでご相談ください。実績と経験豊富な担当者がお客様の不安や困りごとに寄り添い、最適な対処法をご提案します。お気軽にお問い合わせください。
信頼できる不動産会社をお探しの方は、ハウスウェルにお任せください!ぜひご覧ください