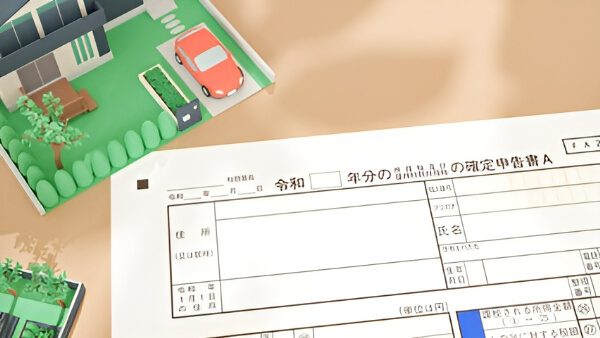家や土地などを相続した際、確定申告は原則として必要ありません。しかし、相続した不動産を売却したときには、確定申告が必要な場合があります。
今回は、相続した不動産を売却した際に確定申告が必要となるケースを詳しく解説します。確定申告の手続きの流れや各種控除なども紹介するので、ぜひ参考にしてください。
1.相続した不動産を売却した場合も確定申告が必要?
 相続した土地や建物などの不動産を売却して利益が出た場合は、譲渡所得税が課され、売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をする必要があります。
相続した土地や建物などの不動産を売却して利益が出た場合は、譲渡所得税が課され、売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をする必要があります。
譲渡所得とは、以下の計算式によって算出した金額です。計算した結果プラスとなる場合は、売却益が出たことになり、売却益に所得税や住民税が課されます。
売却価格とは、不動産を売却した際の金額のことで、売買契約書に記載された金額です。
取得費とは、売却した不動産を購入した際にかかった費用に、改良費や設備費などを加えた金額を指します。ちなみに、不動産を相続した場合は、亡くなった人が購入した際の購入価格が取得費となります。また、建物については、所有期間に応じた減価償却費を購入価格から差し引かなければなりません。
譲渡費用とは、不動産を売却する際にかかった費用のことです。仲介手数料や売買契約書に貼り付けた収入印紙代、立ち退き料、建物の解体費用、測量費などを計上できます。
ここでは、故人が土地2,000万円、建物1,000万円で購入した不動産を相続人が4,000万円で売却し、その際に100万円の仲介手数料を支払った場合を例に見ていきましょう。建物の減価償却費が400万円とすると、特例がない場合の譲渡所得は次のように求められます。
| 4,000万円-{(2,000万円+1,000万円-400万円)+100万円}=1,300万円 |
相続した不動産の売却を検討している人は、ハウスウェルに相談しませんか?お問い合わせはこちら
2.譲渡所得の税率は不動産の所有期間によって変わる
 不動産の譲渡所得の税率は、売却した年の1月1日時点の所有期間によって以下のように異なります。
不動産の譲渡所得の税率は、売却した年の1月1日時点の所有期間によって以下のように異なります。
| |
所得税 |
住民税 |
| 所有期間が5年以下 |
30% |
9% |
| 所有期間が5年超 |
15% |
5% |
つまり、所有期間が5年を超える長期所有の場合は合計で20%、5年以下の短期所有の場合は39%の税率となります。
確定申告の際には、所得税と併せて、基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を控除した金額)に2.1%をかけて算出した復興特別所得税も申告・納付しましょう。
3.譲渡所得がマイナスの場合は確定申告の必要なし
 相続した不動産を売却した際に売却益が出ない場合は、原則として確定申告は不要です。ただし、給与所得や事業所得、不動産所得など、不動産の売却以外で所得があった場合は、確定申告をしなければなりません。
相続した不動産を売却した際に売却益が出ない場合は、原則として確定申告は不要です。ただし、給与所得や事業所得、不動産所得など、不動産の売却以外で所得があった場合は、確定申告をしなければなりません。
不動産の譲渡所得は、分離課税といって、給与所得とは別に計算されます。マイナスの所得とプラスの所得を相殺する損益通算はできないため、注意しましょう。
所有する不動産を高値で売却したい人は、ハウスウェルにご相談ください!お問い合わせはこちら
4.特例を利用するなら確定申告が必要
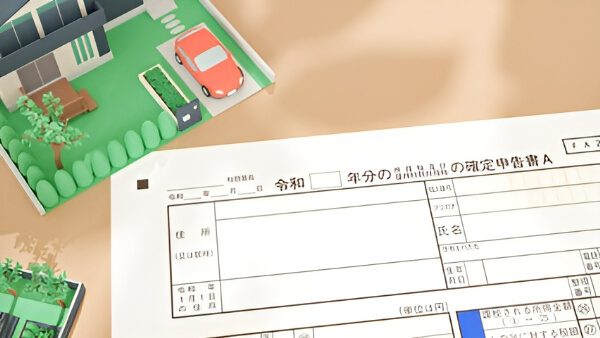 相続した不動産を売却する際、一定の条件を満たすと売却益から一定額が控除されたり、所得税や住民税の税率が軽減されたりする特例を利用でき、節税につながるケースがあります。ただし、特例を利用する場合は確定申告が必要です。
相続した不動産を売却する際、一定の条件を満たすと売却益から一定額が控除されたり、所得税や住民税の税率が軽減されたりする特例を利用でき、節税につながるケースがあります。ただし、特例を利用する場合は確定申告が必要です。
ここでは、特例の詳しい内容をご紹介しましょう。
①3,000万円特別控除
3,000万円特別控除とは、居住用として利用してきた不動産を売却した場合、一定の要件を満たせば売却益から最大3,000万円まで控除できるという特例です。
住宅ローン控除とは併用できないため、マイホームを売却して新たに買い替える場合は、どちらの控除を適用させるかをよく検討しておかなければなりません。
②10年超所有の居住用不動産を売却した際の軽減税率の特例
マイホームを売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていた場合に、適用される軽減税率の特例です。相続した場合の所有期間は、亡くなった人がその不動産を購入してから10年を超えているかどうかで判断します。
一定条件を満たせば、譲渡所得のうち6,000万円までは10%の軽減税率で計算できるため、大幅な節税につながるでしょう。譲渡所得が6,000万円を超える場合は、6000万円を超えた部分に対して以下の税額が上乗せされます。
| (長期譲渡所得金額-6,000万円)×15%+600万円 |
③特定の居住用財産の買い換え特例
特定の居住用財産の買い換え特例とは、居住用として利用してきた不動産を売却した代わりに新しくマイホームを購入した際、売却益を将来に繰り延べられる特例制度のことです。
例えば、1,000万円で購入したマイホームを4,000万円で売却し、5,000万円のマイホームに買い替えた場合、売却益の3,000万円が課税対象となります。しかし、この特例制度を利用すれば、5,000万円で購入したマイホームを売却するまで、譲渡益に対する課税を先延ばしにできるというものです。
出費がかさんでいるなかで、少しでも税金の負担を軽減したいという人におすすめの制度といえるでしょう。ただし、3,000万円特別控除や軽減税率、住宅ローン控除との併用はできないため注意が必要です。
5.確定申告の流れ
 相続した不動産を売却して確定申告が必要になった場合は、忘れずに手続きをしましょう。万が一、申告しなければならないにもかかわらず期日までに手続きしなかった場合は、「無申告加算税」や「延滞税」などの附帯税が課されるため注意が必要です。
相続した不動産を売却して確定申告が必要になった場合は、忘れずに手続きをしましょう。万が一、申告しなければならないにもかかわらず期日までに手続きしなかった場合は、「無申告加算税」や「延滞税」などの附帯税が課されるため注意が必要です。
確定申告の期日は、原則として毎年2月16日から3月15日までの1カ月間です。
確定申告の基本的な流れは、以下のとおりです。
・必要書類を集める
・確定申告書に記載・入力する
・税務署やe-Taxで申告する
・納税する(還付を受ける) |
譲渡所得がある場合は、以下の書類をまとめた上で申告しましょう。
・確定申告書の第一表、第二表、第三表(分離課税用)
・身分証明書類(マイナンバーカード、通知カードと運転免許証など)
・譲渡所得の内訳書
・売買契約書の写し
・譲渡費用に関連する領収書の写し
・控除証明書(生命保険料、社会保険料など)
・源泉徴収票(給与、年金など) |
譲渡所得の確定申告では、通常の確定申告書である第一表・第二表に加えて、第三表の提出が必要です。また、身分証明書や不動産に関連する書類も用意しなければなりません。
利用する特例によっては、他にもさまざまな書類が求められます。必要な書類が分からない場合は、税務署や不動産会社に確認しましょう。
6.まとめ
 相続した家を売却して利益が出たら、確定申告をしなければなりません。また、利益が出ていない場合であっても、各種特例を利用する際は確定申告が必要です。確定申告の手続きを怠るとペナルティとして附帯税が課される恐れもあるため、注意しましょう。
相続した家を売却して利益が出たら、確定申告をしなければなりません。また、利益が出ていない場合であっても、各種特例を利用する際は確定申告が必要です。確定申告の手続きを怠るとペナルティとして附帯税が課される恐れもあるため、注意しましょう。
信頼できる不動産会社に仲介を依頼すれば、確定申告を含むさまざまな手続きをサポートしてもらえます。個人で対応するのが不安な方は、充実したアフターサポートを受けられる不動産会社に相談しましょう。
ハウスウェルは、埼玉県を中心にサービスを展開している不動産会社です。不動産の売買はもちろん、リフォームやリノベーション工事まで、不動産にまつわるあらゆる手続きに一貫して対応できます。
豊富な実績やノウハウを活かして、お客様の不動産の価値を最大限引き上げ、スムーズな取引をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
信頼できる不動産会社をお探しの方は、ハウスウェルにお任せください!ぜひご覧ください